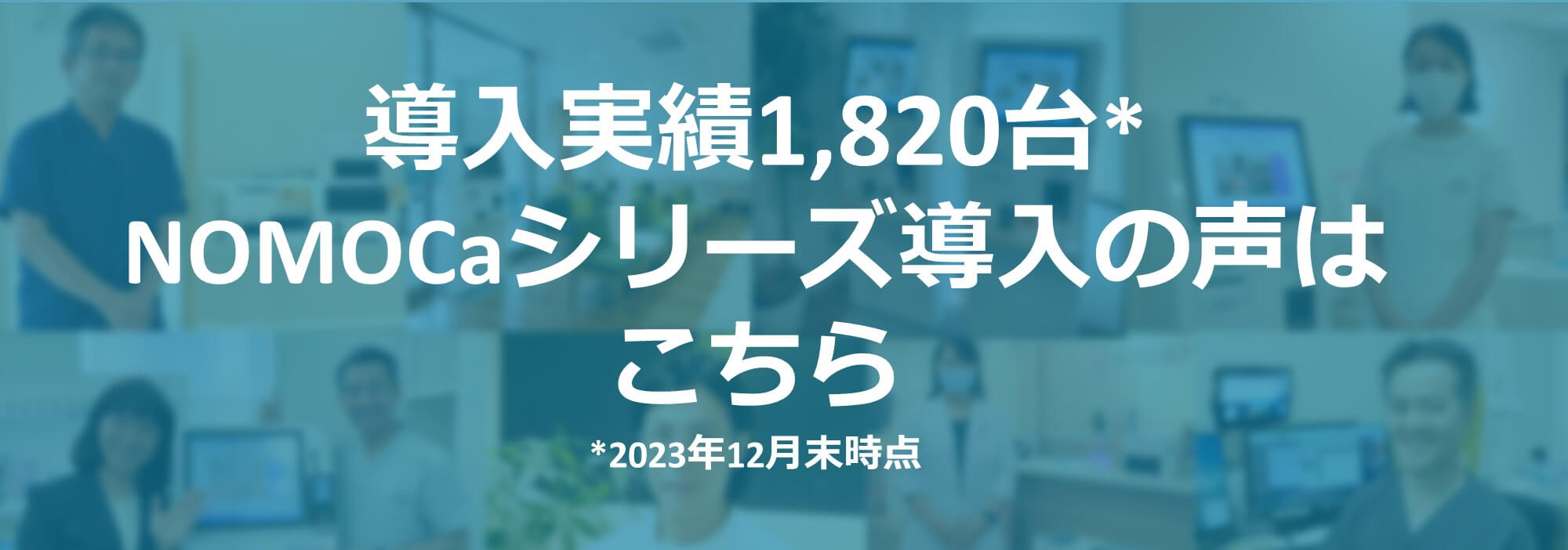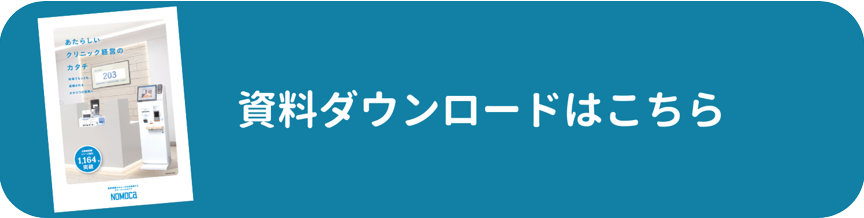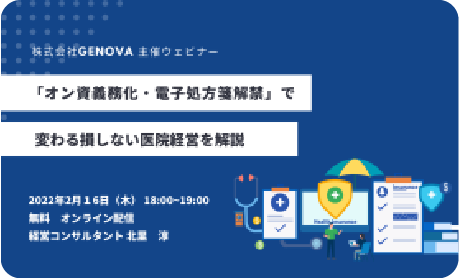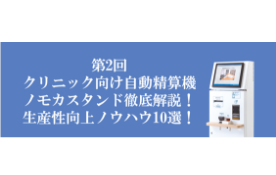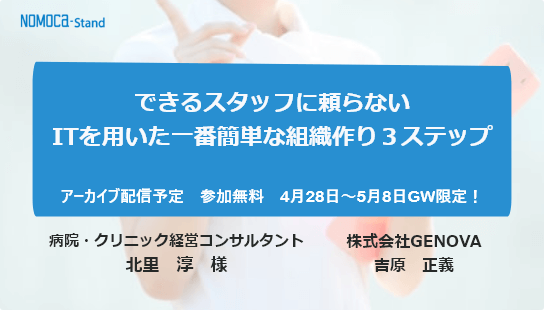ノモカブログNOMOCa-MAGAZINE
【実際どうなの!?】AI問診
更新日:

最近、「AI問診ってどうなの?」と聴かれる機会が増えてきました。「うまく活用できれば、効率化になりますが、逆効果になることもあるので注意が必要かと思います」と返答しています。
今回は、近年、徐々に医療機関に広がりつつあるAI問診について、導入のメリット・デメリット、導入のポイントをお伝えできればと思います。
AI問診とは
医療機関に行けば必ずと言っていいほど行う診療行為の中に、”問診”があります。従来の問診は、紙の問診票に記載し、それで不足する内容を、スタッフや医師が追加で問診をするという流れでした。そのため、医療機関は”問診”に非常に多くの時間を使いますし”問診”の精度によって診察の効率性が大きく変わってきます。
それに対し、AI問診は、スマートフォンやタブレット上で、出てくる設問に対して返答していきます。人手を取らず、かつ、患者さんの自宅などで十分な問診を行うことができるものです。
AI問診のメリット
メリットを挙げてみます。
・場所にとらわれない(患者の自宅からでも答えられる)
・問診票だけではすくい上げられない量の情報を上げてくれる
・スタッフによる問診の精度のバラツキを抑えられる
・多様なリスクを抽出してくれる
・膨大なデータ蓄積されている
上記のメリットの結果、問診だけで膨大な情報を吸い上げることができますので、医師やスタッフが行う問診時間の削減が実現できます。
AI問診のデメリット
実際に医療機関の運用を拝見して感じたデメリットもお伝えしたいと思います。
私は、「様々な可能性を模索しすぎる」ことであると考えています。
これは一見メリットのように思えますが、例えば、、、問診上で「腰の痛み」を主訴とした患者さんがいた場合、腰部の筋、骨、靭帯の可能性もありますが、腹部大動脈瘤やその他の疾患の疑いも模索しはじめ、結果、一つの疾患に絞りきれずに複数疾患が疑いであるという結果になってしまいます。
そのため、患者さん的にも答えなければならない設問が増えてしまい、負担になってしまいます。高齢者に厳しいと言えます。
また、医療機関側もAI問診で可能性を提案してくる疾患名が非常に多くなってしまうので、問診内容を電子カルテに反映する際に手間が生じてしまいます。
そのため、外来単科のクリニックなどでは、AI問診よりもある程度情報を絞って自院独自にアルゴリズムを作成したWEB問診の方がメリットを享受できる可能性があるのではないかと考えています。
ただ、多くの診療科があり、重大なリスクのある患者さんが多い病院ではAI問診がより有効なのではないかと考えます。
その他、AI問診導入の注意点
先述したように、単科のクリニックでは、「アルゴリズムを狭めたWEB問診を活用し、それ以外のリスクは診察時に見極める」というオペレーションの方が良いかもしれません。
そのほかにも注意点としてあげられるのが、AI問診と同じ内容を診察の時に同じことを再度聞いてしまうということです。
これでは、せっかく業務効率化のために導入したにもかかわらず、効率を下げてしまいます。実際にこのようなことは非常に多くの現場で見受けられます。
そのため、ツール導入前にAI問診を入れた目的や意義をしっかりスタッフ全体ですり合わせを行うことが必要でしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、我々のユーザー様でAI問診を導入している医療機関様からのお声や現場見学からから見えたポイントをまとめてみました。
皆様がAI問診をご検討される際にお役立ちできれば幸いです。
関連記事
一覧はこちら導入サポート
-
資料ダウンロード

ノモカについてまとめた資料です。
資料ダウンロード -
お問い合わせ
営業チームが悩みや
お問い合わせはこちら
ニーズをお伺いし、
最適な製品を
ご提案します。 -
サポートセンターに電話
NOMOCa製品を安心して
お使いいただけるよう、
万全のサポート体制を
ご用意しています。